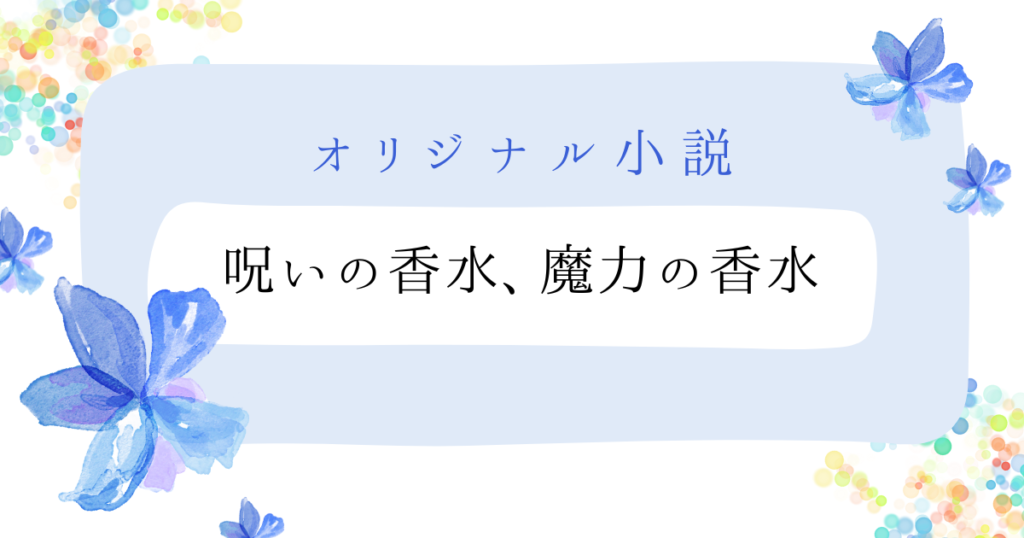
呪いの香水、魔力の香水
香水臭い女は嫌いだ。
べたべたと纏わりついてくる女はみんなプンプンと香水の匂いを放っている。
♢ ♢ ♢
花火をみんなで見ようと誘われて行った友達の家になぜか女がいた。
「……男だけじゃなかったのかよ」
近くにいた男友達のひとりに小声で問いかけてみると「女のコいた方が楽しいじゃんって言って洋平が誘った」とビールに口をつけながら言った。
チッと心の中で舌打ちをする。
女が来ると知っていれば最初からこの集まりには来なかった。
「竜さんってぇ、なんの仕事してるんですかぁ?」
名前も知らない女が、俺の名前を呼びながらすぐそばに座った。
ざっくりと開いた胸元を強調するかのようにして俺の腕にソレを当ててくる。
もれなくその女からも甘ったるい香水の匂いがした。
「…………それ、あんたに教える必要ある?」
「ちょ、竜。もうちょい愛想よくしろって」
「愛想なんてもん持ち合わせちゃいねぇよ」
そんなもん、多分生まれたときから俺にはなかっただろうよ。
だから――――。
『本当、かわいくない子ね』
真っ赤に縁どられた唇から放たれた言葉が脳内で響いた。
その言葉に意識を掴まれないように、今に意識を集中させる。
「悪ぃけど今日は帰るわ」
「え、竜!?」
引き止める友達の声がしたが、振り向く気にはなれなかった。
外に出ると、むわっとした熱気に包まれた。
さっきの女の甘ったるい香水の匂いがいつまでも自分から離れていかない。
そのせいで、また俺の脳裏にある女の影が浮かんだ。
「っ、うえ」
こみ上げてくる吐き気をなんとか抑え、近くの公園に寄った。
公園に設置された水道の蛇口をひねり、さきほど押しつけられた腕と顔をジャバジャバと洗う。
昼間温められてしまったせいで、蛇口から出てくる生温い水は決して気持ち良くはなかったけれど匂いが消えればそれでよかった。
香水の匂いは、全部アイツの――――幼いころ、突然いなくなった母親の匂いのような気がして気持ち悪くなる。
「ねえ、これ使う?」
振り向けば、見知った顔の女が俺に向かってタオルを差し出していた。
「明日香。…………なんでここにいんの」
明日香は幼馴染だ。
ちなみに明日香というのは名字で明日香ななみというのが本名だ。
昔、アイドルみたいな名前だよねと自分で笑っていた。
「バイトの帰りだけど」
「だろうな」
浴衣姿の人間が多い中、明日香はジーンズに黒のTシャツというシンプルな格好だった。
「だろうなってなによ。で、あんたこそ、なんでここにいんのよ」
「……別に」
明日香から差し出されたタオルを受け取り、顔をふくと、そのタオルから雨が上がったあとにふわりと香ってくる花みたいな匂いがした。
柔軟剤か洗剤か。
その甘ったるくない優しい匂いに、ざわざわとしていた心が少しだけ落ち着いた。
「それあげようか」
「は?」
「そのタオルあげようかって言ってんの」
「別にいらねぇし」
「そう?そのタオルにいつまでも顔埋めてるから、てっきり欲しいのかと」
「欲しくねぇって。それに、いつまでも埋めてねぇよ」
いい匂いだとは思ったが、べつにいつまでも埋めていたつもりはない。
「いい匂いでしょ、それ」
肯定の返事をしたらまるで明日香の匂いを好きだと言っているようじゃねぇかと思うと素直に頷けなかった。
「そのタオルね、香水を吹きかけた紙と一緒に一晩タンスの中に入れといたの」
「は、香水…………?」
「そ。香水。その香水のテーマはみずみずしい朝。庭に咲いている花に水をあげたときの匂いの再現をしてるの」
香水だと聞いて、落ち着いていた心がわずかに騒いだ気がした。
けれど、手に持っているタオルからふわりと香った匂いが、そのわずかに騒いだ心を優しくなでていった。
「――――竜がね、香水嫌いなの知ってるよ。だから、私は香水で竜を幸せにしようと思ったの」
明日香の凛とした瞳が熱を帯びてわずかに揺れる。
「匂いは、忘れた記憶を連れてくる。忘れたいはずの記憶もかまわず連れてきてしまう。それだけ、匂いって強烈なの。匂いって魔力のようだっていつも思う」
「…………俺には、呪いだよ」
常にまとわりついて離れない。忘れたくても忘れられない一生ものの呪い。
「その呪いを私は魔力で解こうと思う」
魔法使いかなにかにでもなったつもりか、いつものようにそう茶化すのは簡単だった。
でも明日香の初めて見る真剣な顔に言葉が出てこなかった。
「呪いを解くためには、竜に強烈な出来事とともに匂いを刻みこむこと」
「…………なんだよ、強烈な出来事って」
ドン!!!!
という大きな音とともに夏の暗くなり始めた空に大輪の花が咲いた。
「竜」
花火が止んだときに聞こえた声の方向へと顔を向ける。
みずみずしい花の匂いと共に明日香の匂いがすぐ近くでした。
それと同時に俺の唇に触れた明日香のやわらかい唇。
「ど、どう強烈な出来事になった?」
ドン、ドン、ドンと連続で空へと放たれる花火が、明日香の真っ赤になった顔をはっきりと映し出していた。
俺は、思わず明日香の身体を抱きしめていた。
抱きしめて初めて、明日香の身体が小さく震えているのが分かった。
明日香から香った香水だけじゃない初めて嗅ぐ甘美な匂いに、なぜか涙が一筋頬を伝った。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。
感想を送っていただけると励みになります。
カクヨムというWeb小説サイトにも掲載しております。