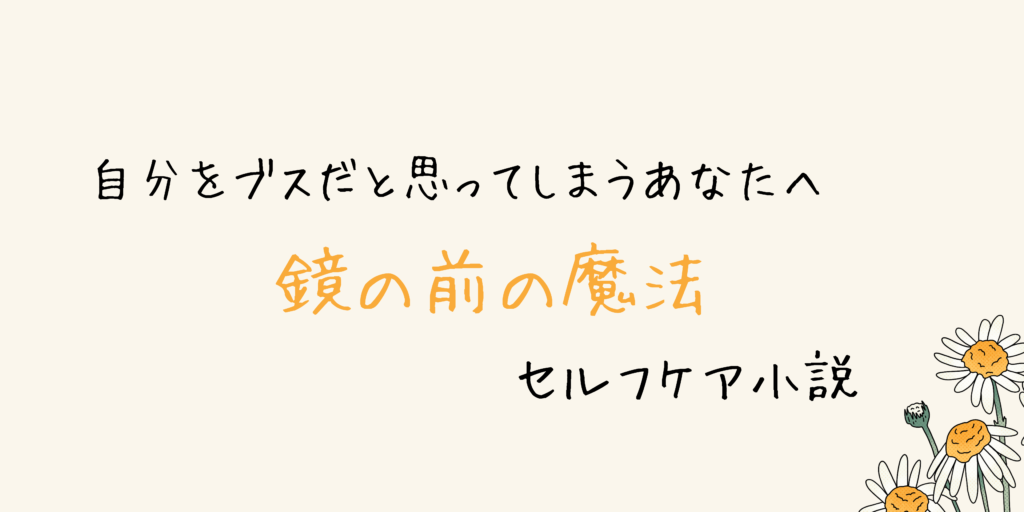
ご覧いただきありがとうございます。
ここでは、読んだあとに心が少しでも軽くなっていただけたら…………という気持ちで書いた小説を載せています。
最後までご覧いただけたら嬉しいです。
セルフケア小説「鏡の前の魔法」

スマホが今日も朝六時を知らせる色気のない電子音を枕元で響かせる。
朝起きるのも少しは嫌じゃなくなるかもと、好きな曲にしたことがあったが、朝起きるのが嫌じゃなくなるどころか、その曲すらも嫌いになってしまいそうだったので、やめた。
ルミは、開かない目のまま、スマホを手探りで探しあて、布団の中に引きずり込みアラームを止める。
あぁ、今日も仕事だ……。
やっと夜だと思ったら、あっという間に朝が来る。
寝ている間に、神様が夜だけ早送りしているんじゃないかと思う。
行きたくない。
ルミがそう思うのは、今日だけじゃない。
毎日、目が覚めて1番に頭に浮かぶ言葉が、これなのだ。
布団を出るのも、朝ご飯を食べるのも、着替えるのも、化粧をしなきゃいけないのも、なにもかもが億劫だ。
若い頃は、もうちょっとマシだった気がする。
今より、仕事に対するやる気もあったし、仕事終わりに友達と出かけてオールしたりする体力もあった。
――肌ツヤだって、もっとあったし、ピンとしたハリもあった。
あぁ、生足で出勤したりもしてたっけ。
それが、今はどういうことなのだろう。
加齢には逆らえないということなのだろうか。
30を越えたあたりから、だんだんと肌はくすんでいってしまったし、ハリは失われ、たるんでしまった。シミだって増えたし、目の下のクマは消えてくれない。
ルミは、鬱々とした思考をなんとか、理性で追い払い、もそもそと布団から這い出た。
それから、顔を洗い、スーパーで買っておいたパンを袋から出し、そのままかじる。
朝ご飯なんて、本当は食べなくても平気なのだが、口うるさい母がしょっちゅう「朝ご飯はちゃんと食べてるの?」と電話してくるので、食べるようになった。
食べるというよりも、咀嚼するという動作を終えると、次は、出社のための洋服に身を包む。
今日は、また一段と冷え込んでいる気がする。
分厚いタイツで足をしっかりと防寒対策しておこう。
着替え終えたら、最後の難関が現れる。
よし。ルミは、自分を奮い立たせる。
ルミにとっての最後の難関、それは――――化粧だ。
最近、自分の顔を鏡で見る度にしんどくなってしまう。
だって、鏡を見ると、自分が老けたって、いやでも分かるんだもん。
ルミは、申し訳程度の化粧を済ませ、家を出た。
♢
「あぁ、今日も疲れた」
仕事終わり、いつものように、ぽそりと呟く。
けれど、今日は、特に疲れた。
会社で、ルミは上から2番目の年長者だ。
まさか自分が、お局様的立ち位置になるなんて思わなかった。
私だって、怒りたくて怒ってないわよ。
それなのに、陰で悪口言われてるの聞いたら、さすがに堪える。
はぁ、と魂も一緒に出てるんじゃないかというほど、大きなため息が出てしまう。
まだ、あと2日もあるのかぁ。
―――――しんどい。
しんどい。しんどい。しんどい。
私は、いったいなんでここにいるんだろう。
毎日決まった時間に起きて、決まった時間に出社して、同じような仕事をして、家に帰る。
家に帰ったって誰もいない。
友達が結婚してからというもの、生活リズムが合わなくなり、全く飲みに行かなくなった。
このまま家に帰ったら、またいつもみたいにあっという間に朝が来る。
そのとき、パンッ!とルミの中でなにかが弾けた。
ルミの足は家と反対方向へ向かっていた。
♢
ルミは、初めて来る場所に来ていた。
ここ、一度来てみたかったのよね。
そこは、家とは反対方向の電車に乗り、5つ目の駅にある場所。
ルミの目の前には、可愛らしいお店があった。
会社で、若い子たちが話していた、美味しいと評判のパン屋さん。
今日は、ここでパンを買って帰ろう。
そして、明日の朝ご飯にしよう。
そう思って、扉を開けようとして、貼り紙を見つけた。
ルミは、その貼り紙を見て、泣き出したい気持ちになる。
「定休日……」
もう、なんで。
なんで今日はとことん、こんな日なの。
もう、だめ。泣く。
ルミの視界が滲んだとき、後ろから声が飛んできた。
「大丈夫か?」
声の方を振り向くと、ガタイの良い男の人が立っていた。
ひっ、と息を呑む。ルミの身体は、こわばってしまっていた。
「顔色、悪いぞ」
そう言ってどんどん近づいてくるガタイの良い男性。
「あ、あの、大じょう、ぶ、です」
ルミは、なんとか声を絞り出す。
「どう見ても大丈夫じゃないけどな。うちの店で休んでいくか?」
ルミは、ぶんぶんと首を横に振った。
「……怪しい店じゃないよ、ほら、俺の店、そこの花屋だよ」
男性は、ぶきっちょな笑みを浮かべながら、指差して言った。
その笑った顔が、なんだかあまりにも邪気がなかったから、ルミは、安心して、腰が抜けてしまった。
それを見て、またその男性は笑った。
今度は、口をあけて豪快に。

男性のお店だという花屋は、押し扉を開けた瞬間、花の甘い匂いに包まれた。
「そこ、座ってて」
男性は、白の椅子とテーブルが置かれた場所を指して言った。
花屋さんのなかにこんな場所があるなんて、まるで貴婦人のお庭みたい。
ルミは、目を瞑って、その空間に身を委ねた。
「少しは、落ち着いたか」
男性が、ティーカップとともに戻って来て言った。
「あ、はい。ご迷惑をおかけしました」
「少しも迷惑なんて思ってないから安心してくれ。
これは、カモミールティーだ。気分が落ち着く。良かったら飲んでくれ」
差し出されたティーカップからは、ふわふわと湯気が出ていた。
「かわいい……」
透き通った黄金色のお茶の中には、黄色く盛り上がった中心に白い花びらをつけた花が2つ浮いていた。
「カモミールだ。かわいいだろう」
男性の言葉が、容姿とあまりにもかけ離れているので、ルミは思わず吹き出しそうになった。
「いただきます」
静かにわきあがる笑いをかみ殺し、ルミは、ゆっくりとティーカップに口をつける。
すると、すっきりとした甘さが口の中に広がり、ゆっくりと、お腹の中へと落ちていった。
鼻からは、優しい甘い匂いが入ってくる。
なんだか、あたたかく大きなものに、包み込まれているような気がしてしまった。
「良かった」
男性は、ゆっくりと呟いた。
微笑んでいるのか、真顔なのか、いまいち読み取りにくかったが、目には優しさが宿っている。
「顔色、だいぶよくなったな」
「あの、私、そんなに顔色、悪かったですか」
「あぁ、一目見て分かるほどにな」
なんだか、恥ずかしくなってしまい、ルミは黙り込んだ。
「なんかあったか」
どっしりとした声が耳に届いた。
「顔色悪くなるほどのことが、あったのか?」
ルミは、太ももに置いた手をぎゅうっと握る。
「あぁ、悪い。話したくないなら話さなくていいんだ」
男性は、そう言って立ち上がった。
「あの、聞いてくれますか」
男性は、椅子に座りなおし、「あぁ」と短く答えた。
「私、今年で32になるんです」
ルミは、ぽつり、ぽつりと胸の内を話し出した。
恥ずかしくてずっと下を向いたままだったし、上手く喋れているか分からなかったけれど、男性は、ずっと聞いてくれていた。
「会社の若い子たちが言ってたんです。
私がいると、場が暗くなるって。仕事できないし、ブスのくせに、指図するなって。
仕方ないですよね、私、本当にブスだし」
ルミが話し終えても、男性は何も言わなかった。
おそるおそる顔をあげると、ひどく厳しい顔をした男性が、ルミを見つめていた。
「君は、自分がブスだと本当に思っているのか」
真っ直ぐに向けられたその質問にルミは、何も言えなかった。
「ブスだと思っているのは仕方ない。けどな、自分で口にしては絶対にダメだ」
男性の言い方は強かったけれど、真っ直ぐに向けられた瞳はすごく優しかった。
「いいか?“ブス”と毎日言い続けた花と“綺麗だね”と言い続けた花。
この2つの花は、1週間後、大きな差が出る。どんな差が出るか分かるか?」
ルミは、静かに首を横に振った。
「“ブス”と言い続けた花は、ものすごい悪臭を放ちながら枯れるんだ。一方、“綺麗だね”と言い続けた花は、1週間後も、まだ元気に咲いている」
枯れる……・
その言葉が、ルミの心をえぐる。
「女性はずっと美しい花だ。
それも、歳を重ねるほどに、強さとしなやかさを兼ね備えていき、味わい深い花になる。この味わい深さは、歳を重ねた花にしか持てない。
ブスだと声をかけ続けると、すぐに枯れる。
いいか、大事なのは、咲き続けようとする気持ちだよ」
咲き続けようとする気持ち――。
ルミは、ゆっくりと口を開いた。
「……もう、枯れかけている私には無理でしょうか」
「誰が枯れかけてるって?
君は、枯れかけてなんかいない。
今は少し元気がないだけだ。水をあげて、日光を浴びて、肥料を与えてあげれば、まだまだ綺麗に咲く。今までよりも、もっと綺麗な花が咲くはずだ」
「でも、私、鏡を見る度に思ってしまうんです。老けた、元気がない、ブスだって。毎朝、鏡にそう言われている気分になってしまうんです」
「魔法使うか?」

「魔法?」
男性の口から出た言葉が、ルミはすぐには理解できなかった。
「鏡の呪縛を封印する魔法を授けてやる」
「あの、それってどういう……」
「鏡の前に好きな花を1輪飾るんだ」
「花、ですか」
「そう。そして、その花を“かわいい”、“美しい”と思う。
自分に、鏡に映る自分を見せてやるんじゃなくて、花を見せてやる。
そうしたら、鏡の前に座った時、ブスだって思う瞬間がなくなるだろ?
かわいい花。最初はそれでいい。徐々にかわいい私って思えるようになる、はずだ」
男性が、やけに自信たっぷりに言うものだから、ルミは、そんな気がしてしまう。
「ちょっと、待ってな」と男性は席を立った。
「これは、私からのプレゼントだ」
男性は、綺麗に包まれた黄色い花を1輪持ってくると、それをルミに手渡した。
「ガーベラですか」
「あぁ。黄色のガーベラ。
ガーベラは、気どらないかわいさをもっている。君にぴったりだろう?」
そう男性から説明されたとき、ルミは顔が熱を帯びているのが分かった。
男性にお礼を言い、ルミは家路へついた。
ルミの口元は、きゅっと上を向いていた。
おわりに
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
現在、noteで利用しませんかという恋愛小説を連載中です!
興味のある方は覗いていただけると嬉しいです。