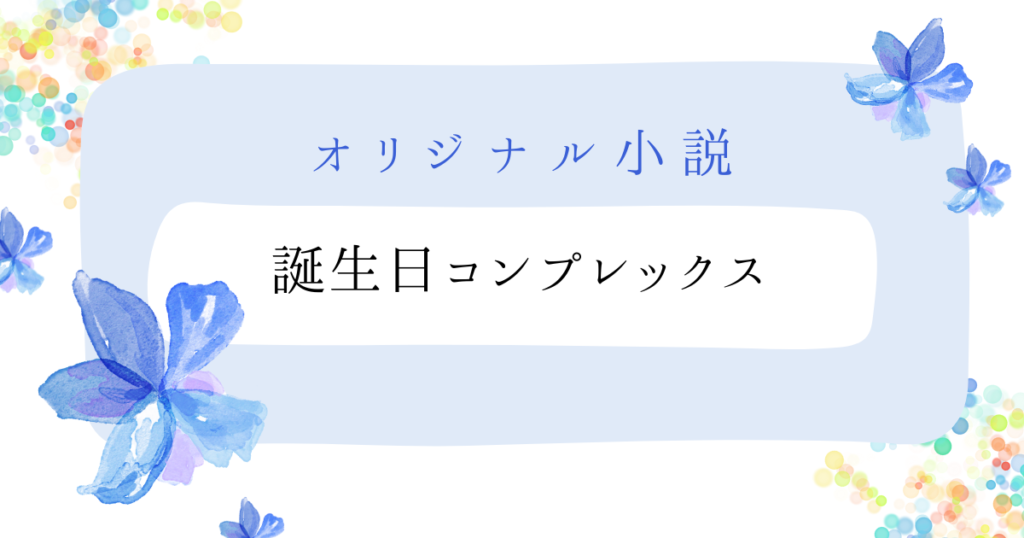
ご覧いただきありがとうございます。
私は小学4年生のころから小学6年生のころまでいじめに遭っていました。
中学、高校と友達と呼べる人がいない日々を過ごしていました。
こちらの記事では、いじめを受けていた私が書いたエッセイとなっています。
最後までお付き合いいただけると嬉しいです。
「誕生日コンプレックス」

自分の誕生日が近づいて来るにつれ、期待とは違った何かが胸の中にもくもくと沸き起こって来る。
「ごめん、さわこ」
私の誕生日の1週間前、申し訳なさそうに切り出した夫に、何かと思って耳を傾ければ、「さわこの誕生日、休みとれそうにない」という謝罪通告だった。
「大丈夫だよ!わざわざ仕事休みとってくれなくても」
そう言ったのは、本心だ。
だって、自分の誕生日のためにわざわざ仕事を休ませてしまうのはどうしても気が引ける。
あっけらかんと言ったつもりだったのに、夫の申し訳ないという表情は変わらなかった。
「いや、けど……。誕生日は、」
「大丈夫だって、本当に」
何か言いかけた夫に、笑いながら言った。
――それなのに、胸が少しだけ痛んだ。
♢
「誕生日おめでとー!」
同じクラスの女子たちは、友達のだれかが誕生日のたびに声を大にして、その言葉を叫んでいた。
「おめでとう」と言われた方は嬉しそうに、「ありがとう」と微笑む。
プレゼントを渡されると、より嬉しそうにしていたっけ。
私の頭の中に、ぼんやりと学生時代の記憶が浮かんだ。
♢
もうあと3日で私の誕生日か。
今年も夫は仕事だし、息子も幼稚園だ。
平日だもんね。1人きりの誕生日。なにをしよう。
――いや、無理になにかする必要があるわけじゃない。
でも、誕生日ってやけに意識をしてしまう。
自分の誕生日を忘れてしまう人も世の中にはいるのかもしれないけれど、私は逆だ。
自分の誕生日をやたらと意識してしまう。
特別視してしまう。
そんな特別感あふれる日だからこそ、「何か特別なことをしたい!」と、毎年、そう思わずにはいられないのだ。
それで、なんにも特別なことがなかったら、落ち込んだり、拗ねたりしてしまう。
そんな自分が、自分で面倒くさくて嫌だった。
♢
4月15日。15回目の誕生日。
その時の誕生日も平日で、学校にいた。
そわそわ、そわそわ。
今日でわたし15歳になるんだ。
「さわこ、おめでとう」
学校から、家に帰ると、母や父が満面の笑みでそう言ってくれた。
食卓の最後には、わたしの大好きないちごケーキが登場した。大きいロウソク1本と小さいロウソク5本につけられた炎がゆらゆらと揺れている。
大きく息を吸い込み、ふぅっ!と思いっきり消す。
少し煙たくなった部屋の中で、家族みんなでいちごケーキを食べた。
♢
あぁ、なんか胸のあたりが重たい。
明日は自分の誕生日。
私の心は、わくわくというよりも、なんだかもやもやしたものが胸のあたりをざわつかせている。
「やっぱり、さわこ変だよ。どうかした?」
息子を寝かしつけたあと、夫が言った。
「いや、別に」
私は、夫の問いにそっけなく答えてしまった。
2人の間にしばし重たい空気が流れた。
少しして、夫がその静寂を破った。
「……ごめんね、誕生日。一緒に過ごせなくて」
相変わらず、申し訳なさそうに言う夫。
夫は、私のことをすごく思いやってくれてるんだと、すぐに分かる。
けれど、私の心はもやもやにピリピリまで混ざってしまっている。
「だから別にそれはいいって言ってるでしょ!!」
自分でもびっくりするような大きくトゲトゲしい声を夫に投げつけてしまった。
―――――なんで。なんでこんなに私はイライラしてるの。
誕生日を意識して、意識して、意識しまくって、イライラして夫にあたってしまうくらいなら――。
「……もう、誕生日なんて失くしてしまいたい」
ぽたり、と涙が一粒だけ床に落ちた。
♢
4月15日。18回目の誕生日。
高校最後の誕生日も平日だった。
そわそわ、そわそわ。
そんなそわそわは、次第にしぼんでしまう。最初からそわそわなんてしなければ良かったと思うほどに。
「ただいま」
学校から、家に帰ると、その日は、家族全員揃っていた。
「もう、さわこも18かぁ。はやいな」
「あっという間に大人になっちゃうね」
父と母、それから弟と妹、離れて住んでいるおばあちゃんから「おめでとう」という言葉をもらって、毎年恒例のいちごケーキを食べた。
♢
もう誕生日なんて失くしてしまいたい――。
その言葉と一緒に、涙と一緒に、辛い記憶がこぼれてくる。
「私、学生の頃、一度も家族以外の人からおめでとうって言われたことないの」
辛い記憶は、言葉となって、こぼれてしまった。
下を向いているせいで、夫がどんな顔をしているのかは分からない。
「4月だから、覚えてもらいにくいとかじゃなくて。ただ、単純に、私、友達って呼べる人がいなかったから」
辛いくて苦い記憶。
それが、どんどん、どんどん、声となってこぼれていく。
「おめでとうって誰からも言われないのが辛かった。だって、別に私なんかこの世に存在しなくてもいいって、生まれてこなくてもいいって、言われているような気がして」
本当は、ずっと、誰かに言ってほしかったのだ。おめでとうって。
「おめでとう」っていう言葉は、あたたかい。
だって、「生まれてきてくれてありがとう。そこにいてくれてありがとう」っていう意味だと、私は思うから。
誕生日に「おめでとう」と言葉をかけられないたびに、私は自分で自分の存在価値を否定していた。
毎年、誕生日が来る度にその辛さを思い出さないようにしようと、寂しさを埋めようとしていた。無意識のうちに。
だから、誕生日を嫌というほど意識してしまっていた。
「さわこ。俺、いるから。さわこの過去にも」
降ってきた優しく柔らかい、耳ざわりの良い夫の声。
顔を上げれば、その声の主は優しく、とても優しく笑っていた。
「今度、また、さわこが辛かった過去を思い出したら、その過去に俺も登場させて。俺はどこにでもいるから。俺は、ここまで生きてきてくれたさわこに、おめでとうって伝えたいから」
夫の声は力強く、潤んでいた。
翌日、夫は私が起きるやいなやすぐに「おめでとう」をくれた。
夫のくれた「おめでとう」には、たくさんの想いが込められているような気がして、目の奥の方が熱くなった。
自分の中にずっといた小さな自分にやっと気づくことができた。
その自分はずっと泣いていて、その涙を拭ってくれたのは、夫だった。
「ありがとう」
やっと、心の底から、夫にそう言えた気がした。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました!
アラサーにして、やっと誕生日前に訪れるもやもやの正体を突き止めることができました。